こんにちは。


意外とさらし粉について詳しく解説している参考書ってないんですよ。その割に高校化学でよく出てきます。
特に「アニリンとの反応」や「さらし粉が酸化剤としての酸化還元反応」などが時々大学受験で出題されます。
本記事では「そもそもさらし粉の正体って何なのか?」というところから、「さらし粉ではどのような反応式をかけるようにしなければならないのか」を徹底的にまとめて行きます。
入試問題を解いていく上で必ず必要になる知識ですので、ぜひきっちり身につけておいてください。

と思ってこられた方は、下の目次から「半反応式の作り方」を選んでジャンプしてみてください。
↓本記事の動画バージョンも作成してあります。読むのが面倒な人はこちら↓
目次
さらし粉とは?正体を理解するために化学式を2倍せよ

さらし粉とは何か教科書で調べてみると以下のような書かれています。
「塩化カルシウム」と「次亜塩素酸カルシウム」の複塩で「次亜塩素酸塩化カルシウム」と言います。
※複塩とは、CaCl(ClO)・H2OのようにCa2+やCl–、ClO–のような複数の塩が結合してできている塩のことをいう。(H2Oは配位結合をしている)

いまいちこの説明を聞いてもピンとこないんですよね〜
さらし粉の定義を教科書で読んだとしても、いまいちピンとこないですよね。

さらし粉の化学式を見てもCaCl(ClO)・H2Oを見てもピンとこないはずです。
そこで!!!
この化学式を2倍にしてみるとそのさらし粉の正体が分かります。じゃあ一緒にやっていきましょう。
両辺のイオンの数を倍にしてみます。
実はこれでかなりわかりやすくなりました。

CaCl2・Ca(ClO)2・2H2O
これでこのさらし粉の正体がかなり見えやすくなりましたよね?
さらし粉は『塩化カルシウム』と『次亜塩素酸カルシウム』を混ぜ合わせた塩であると言う事が分かります。
さらし粉の性質
- 殺菌作用
- 漂白作用
殺菌作用や漂白作用は高校科学では「酸化剤の作用」だと思ってください。
殺菌作用は「菌から電子を奪い取ること」です。漂白作用は「色素から電子を奪い取ること」です。
酸化剤は「相手を酸化する=相手から電子を奪うもの」です。

さらし粉は殺菌作用があります。
さらし粉は先ほど複塩と説明しました。
さらし粉は「塩」です。つまり「イオン結晶」なんですよ。
一応補足しておきます。中和反応によってできる物質のことを「塩」と言います。
そして塩は通常イオン結合をしていることが多いです。
さらし粉は塩でありイオン結晶ですので、水に溶かすと電離します。
だからさらし粉を水に溶かすと、Ca2+、Cl–、ClO–になります。
このうち、ClO–(次亜塩素酸)が酸化力を持つのです。
この酸化力が強い『殺菌・漂白作用』を出すのです。
だからさらし粉はプールの洗い場での消毒に使われることが多いです!
高度さらし粉とは?
高度さらし粉とはさらし粉CaCl(ClO)・H2OからCaCl2を取り除いたものです。
CaCl2・Ca(ClO)2・2H2O
これがさらし粉の本来の姿でした。
実はCaCl2って邪魔なんですよ。(この理由はすぐに解説するので読み進めてください)
だから邪魔なCaCl2を取り除いたものを高度さらし粉と言います。
Ca(ClO)2
が残ります。
これが高度さらし粉です。



あ、そっか! ClO–が多い方が酸化力が強くなって、安定して殺菌作用や漂白作用が供給できそうな気がする!

普通のさらし粉は、CaCl2とCa(ClO)2の複塩です。
普通のさらし粉だとCaCl2のせいでClO–の酸化力が弱まってしまいます。
なぜCaCl2はさらし粉にとって邪魔なのか?
塩化カルシウムCaCl2は潮解性があります。
潮解性は下の画像のように、空気中の水分をどんどん吸着して水浸しにしてしまうのです。

塩化カルシウムの潮解性に関しては、「【乾燥剤】塩化カルシウムの性質から用法までが5分で分かる徹底解説!」で解説しています。
さらし粉の中のCaCl2も潮解性により水を吸収します。
CaCl2が水を吸い込むことで、CaCl(ClO)は水に溶けてイオンになってしまいます。

ClO–って弱酸のHClOが電離したものでもあります。
みなさん、思い出してください。
弱酸は100%電離していてはいけないんです。
一番わかりやすい弱酸といえば酢酸が思い出されますよね。
CH3COOH⇄CH3COO–+H+
このような平衡状態になります。
まずは次亜塩素酸イオンの化学平衡状態の式を見てみましょう。
HClO⇄H++ClO–
ちなみにさらし粉が水に溶けてイオン化した時が、以下のような状態になります。

ClO–イオンが100%電離している状態になります。
これは弱酸としてはおかしな状態です。弱酸の場合は「電離していない状態」も存在しなければなりません。
弱酸は100%電離することはなく、右辺のClO–しかない状態を許してくれません。

化学平衡では「左辺と右辺のどちらかの物質しかない状態」を許してくれないです。

したがって、化学平衡はClO–を減らしてHClOを増加させる方向に進みます。

ルシャトリエの原理より左辺に平衡移動するので、ClO–が現象してHClOが生成されます。

HClOは気体ですのでさらし粉の外へガンガン出ていきます。


その通り!
だからさらし粉の中で潮解性を持っているCaCl2は取り除いてしまった方が、さらし粉が水に溶けてしまわずに済むので、性能が長くよく保てるんだよ。
だから、高度さらし粉はさらし粉からCaCl2を取り除いたCa(ClO)2なんです。
この流れはめちゃくちゃ大事です。
弱酸が完全電離している状態が「あれ、おかしい!」と言えるようになってください。
これができると化学平衡で非常に重要な「塩の加水分解」の理解も進みます。このようなルシャトリエの原理で考えられるように、ここまでの説明は友達に解説できるくらいになってください。

さらし粉の半反応式の作り方
先ほど話しました通り、さらし粉のCaCl(ClO)・H2Oの中でもClO–が酸化力を持ちます。
なので、半反応式もClO–→Cl–になるところから作っていきます。
- 左辺に反応物(反応前の物質やイオン)、右辺に生成物(反応後の物質やイオン)を書く
- OとH以外の原子の数を合わせる
- 両辺で酸素が足りない辺にH2Oを加える
- 両辺で水素が足りない辺にH+を加える
- 両辺の電荷をe–で等しくする
ステップ1:左辺に反応物、右辺に生成物を書く
ClO–→Cl–
ステップ2:OとH以外の原子の数を合わせる
Clの数は両辺で等しいので、何もしない。
ステップ3:両辺で酸素が足りない辺にH2Oを加える
ClO–→Cl–+H2O
ステップ4:両辺で水素が足りない辺にH+を加える
ClO–+2H+→Cl–+H2O
ステップ5:両辺の電荷をe–で等しくする
ClO–+2H++2e–→Cl–+H2O
このようにさらし粉の半反応式を作って行きます。
重要なのはさらし粉で酸化力を持つのは、電離した時に出てくるClO–(次亜塩素酸イオン)であることです。
さらし粉で有名な反応
さらし粉に塩酸をぶっかけて塩素を生成する反応
さらし粉の化学反応で「塩素」の生成反応があります。
「さらし粉+塩酸」で塩素が生成されるんですよね。
この反応を受験生の多くは丸暗記するものだと勘違いしています。


さらし粉と塩酸を加えて
ステップ1:さらし粉と塩化水素が弱酸遊離反応を起こして次亜塩素酸が発生する。
ステップ2:発生した次亜塩素酸と塩化水素が反応して塩素が発生する。
ステップ1:さらし粉と塩化水素が弱酸遊離反応を起こして次亜塩素酸が発生する。
さらし粉に塩酸をかけると、HClOが出現します。
強酸ほど本来イオンであるべきです。だけど、Ca(ClO)2として次亜塩素酸カルシウムとして、次亜塩素酸がイオン化しているのです。


このように弱酸の次亜塩素酸イオンは分子の次亜塩素酸になり、塩化水素は塩化物イオンに変わります。
これは高校化学で非常に重要な反応であり、「弱酸遊離反応」です。詳しくは、「酸塩基『弱酸遊離反応』とは?ドラえもんに例えて覚える方法」の記事をご覧ください。
これでHCl(溶液)とHClO(弱酸遊離反応でできたもの)ができました。
CaCl(ClO)・H2O+HCl→CaCl2+HClO+H2O
残ったHClとHClOで酸化還元反応が起こります。
ステップ2:発生した次亜塩素酸と塩化水素が反応して塩素が発生する。
HClのClは酸化数-1、
HClOのClは酸化数+1
そしてこのとき、塩素で酸化数0はCl2のみ。だから2つからCl2が発生する反応を考えればいいのです。
(R)2Cl–→Cl2+2e–
(O)2ClO–4H++2e–→Cl2+2H2O
この2つの半反応式を足し合わせると、
2HCl+2HClO→2Cl2+2H2O
となる。
ステップ1とステップ2の化学反応式を足し合わせますと以下のようになります。
これは塩素の発生反応として重要な反応ではありますが、覚える必要性は0なんです。だから毎回ちゃんと作り出せるようにしておきましょう。
ちなみに、さらし粉と高度さらし粉の半反応式は同じです。
なぜなら、両方とも酸化力を持つのがClO–なので反応自体はさらし粉も高度さらし粉も変わりません。。
アニリンの検出反応に使えるさらし粉
これもさらし粉の酸化力を用いた反応です。
さらし粉の酸化力でアニリンが反応して赤紫色に呈色するのです。
このような文章があれば、『アニリンあり』という風に構造決定でも決める事が出来ます!
かなり発展的な内容になり、覚える必要は全くないんですが、
アニリンとさらし粉を反応させると赤紫色になるのは、プソイドモーベインという下のような構造を持つ化合物が生成するからです。

この構造が赤紫色に呈色するのです!
まとめ
さらし粉(CaCl(ClO)・H2O)とは、塩化カルシウムと次亜塩素酸カルシウムの複塩
さらし粉の性質は、化学式を2倍するとよくわかる。
Ca2Cl2(ClO)2・2H2O
並べ替えると、
CaCl2・Ca(ClO)2・2H2O
なので、「塩化カルシウム」と「次亜塩素酸カルシウム」の複塩だということがわかる。
さらし粉には「殺菌作用」「漂白作用」があり、プールで使われることがある。
これら殺菌作用はCaCl(ClO)・H2Oの中のClO–の酸化力による作用です。
高度さらし粉とは、Ca(ClO)2のことです。
さらし粉からCaCl2を取り除くことで、さらし粉の酸化力が増してさらに長持ちするようにしたものを高度さらし粉と言います。
この辺りの解説は徹底的にやったので、思い出せない人は該当部分を読み直してください。
どうでしたか?案外さらし粉って重要な鍵を握っているし、今回の事が分かればさらし粉の反応、性質、など分かってくるのではないでしょうか?
最後まで読んでいただきありがとうございました!











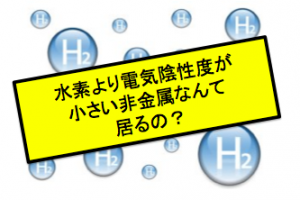




(O)2ClO–4H++2e–→Cl2+2H2O
この式はどこから出てきたんですか?
あと、
CaCl(ClO)・H2O+HCl→CaCl2+HClO+H2O
と
2HCl+2HClO→Cl2+2H2O
を合わせたら
CaCl(ClO)・H2O+2HCl→CaCl2+2H2O+Cl2↑
になる理由がわかりません。
単純に足したり割ったりしてもうまく行かないです、、、、
2ClO–からCl2が出来ると言う事は、
記事にも書いてある通り分かると思います。
これをつかえば、半反応式はつくれます。
そしてもう一個の質問は、
酸化還元の式を間違っていました。
修正しましたが、
Cl2ではなく2Cl2でした。
申し訳ありません。
これを見れば、実際に作り出している様子を
描いているので分かると思います。
ありがとうございます。
おかげさまで理解できました!
おもしろかったです!
「2倍にする」
非常にわかりやすくなりました!!ありがとうございます!!
いえいえ、どんどん活用していってくださいね!!
さらし粉は塩化カルシウムと次亜塩素酸カルシウムの複塩である、の意味が分かりました。
さらし粉の分子式が、覚えやすくなります!
そうですね!そういうことです1
次亜塩素酸やそのほか塩素酸の酸化力や酸の強さについて教科書にまとめてあるのですが、どういう仕組みになっているのですか?次亜塩素酸が酸化力が大きいことや過塩素酸が酸の強さが強いという理由がいまいち分かりません
このサイトに、次亜塩素酸や過塩素酸について書いてある記事がありますよ。塩素と調べて、1番上に乗っている記事です。
https://xn--qck0d2a9as2853cudbqy0lc6cfz4a0e7e.xyz/inorganic/cl-oxyacid
Ca(ClO)2からHClOが遊離して行ってしまう。
と
有効成分を失ってしまう。
とはどういうことですか?
HClOには酸化作用があると思うのですが。。
CaCl(ClO)H2O→Ca(OH)2+ Cl2
の、様にはならないのですか??
ならないです。
可逆反応じゃないです。
さらし粉の名前について、何か由来はあるのでしょうか。
辞書などで調べてみたのですが記載がなく、もう少し自分でも調べてみようと思います。
名前の由来が解ると、おお!となるとおもうので‥
いつもサイト見させてもらってます。CaCl(ClO)H2OはHClを入れずとも適当な酸に入れるだけで(例えばHNO3)
Cl^- ClO^-が水溶液中に溶解する状態になりCl^- +ClO^-+2H^+→Cl2 +H2Oが進行し、結果
CaCl(ClO)H2O+2HNO3→Ca(NO3)2+2H2O+Cl2
となる。という予想は正しいでしょうか?
また、ClO^-はH^+の存在下でのみ酸化剤として働くのでしょうか?
>Cl– +ClO–+2H+→Cl2 +H2O
↑
まずですが、こちらは「酸塩基反応」ではありません。
酸化還元です。
なので、まず適当な酸でも反応が進むということが誤りです。
硝酸を入れた場合硝酸が酸化剤として働きます。
どれだけ上手くいくかはわかりませんが、
Cl–(還元剤)とHNO3(酸化剤)の反応になると思われます。
濃硫酸、十酸化リン、塩化カルシウムが乾燥剤として働くのはどうしてで、どのようにして吸湿するんですか?
ソーダ石灰の場合はソーダ石灰についてのブログを拝見させてもらい納得したのですが…。
プソイドモーベインの化学式がアニリンブラックのものになってると思います。確認お願いします。
ありがとうございます!
修正いたしました。
(R)2Cl–→Cl2+2e–
(O)2ClO–4H++2e–→Cl2+2H2O
ここでなぜ上の式ではHが出てこないのか、また下の式のH+の係数である4はどこから来たのかがわかりません。ここはどのような意味なのでしょうか?
それは酸化還元の超基本的な内容ですので、こちらの記事をご覧ください。酸化剤と還元剤の半反応式の作り方!極限まで暗記を減らす方法
水を生成するために酸素の係数と比較して水を2つ生成するために水素4つが必要になります
アニリンとさらし粉の反応の詳しい化学式が知りたいです。
初めて見ましたが
酸化剤は「相手を酸化する=相手から酸素を奪うもの」と書いてあるのです
これは相手を酸化する=相手に酸素を与える
の間違いではないですか(^▽^)/
ありがとうございます。
正確には「電子を奪うもの」でした。
ご指摘ありがとうございます。
さらし粉と高度さらし粉のとこくそわかりやすかったです!
なんで塩化Caが抜けんねやと思ってたんで助かります
お役に立てて良かったです!