現役生では対策が薄くなりがちな
高分子の範囲ですが、
実は『天然有機化合物』は2次試験で
かなり頻繁に出題されます。
2次試験の大問構成で
最も多いのが、
大問4問構成で、
1問が理論化学
もう1問が無機と理論の融合
そして、残りの2問は
有機化学と言うパターンが
非常に多いです!
そしてこの2問のうち
1問が(芳香族までの有機化学で、
『構造決定』の問題)
構造決定の勉強法については
こちらの記事で書きました。
受験で有機化学構造決定を確実に完答するための勉強法
もう1問がこの
『天然有機化合物』
から出題されます。
大体4問の配点は同じで、
『有機化学が1番点数が取りやすい』
のですが、
そのなかでも天然有機物は
特に努力に比例して点数が伸びる
分野です。
にもかかわらず、
現役生は構造式に圧倒されて、
あきらめがちです。
本当は結構すぐに完成する分野なのに、、、、
実際旧課程でセンター試験で
天然有機物が範囲外だったときは
ほとんどの受験生がセンター後に
勉強手をつけ始めることが多かったです。
なので、
今日はこの天然有機物を
どのように勉強すれば最も早く
攻略できるか?
について公開していきます。
目次
嫌になるくらい暗記が多い?
導入で暗記すべきことが多い
「え、この構造を覚えるの?」
と思ってしまう。
まず天然有機化合物で習うのが、
『糖』ですが、
いきなりグルコースを覚えろ!
と言われてビビってしまいます。

グルコース
しかもグルコースを覚えてあとは、

フルクトースで〜す

ガラクトースで〜す



こいつら全部覚えろ!
と言われて
「は、糖ってメンドクさ、、、、、」
と心を閉ざしてしまう人が多いです。
ですが、
実は、覚えるべき構造は、
ある方法を使うことで、
『グルコース』だけになるのです。』
それは、
『フィッシャー投影法』を
使って構造を覚える方法です。

こんな感じで、
糖の環構造をバラした、
魚の骨みたいな『鎖状』の構造式
のことをフィッシャー投影式と言います。
フィッシャー投影式に関しては
こちらの記事で書きました。
『単糖の構造式は暗記不要!?〜フィッシャー投影式の使い方〜』
これを使うことによって、
グルコースのフィッシャー投影式を
少しいじれば、全ての単糖を
作り出すことが出来ます。
反応は芳香族までと全く同じ
今まであなたが勉強してきた
有機化学の知識は、そのまま使えます。
アルデヒドがあれば
フェーリング反応も銀鏡反応も
します。
ヒドロキシ基、カルボキシ基などの
官能基やC=Cの反応性も
同じです。
反応で新しいことは
『全くない!』
ということです。
新課程になって重要度を増す天然高分子
天然高分子でどの分野を重点的にやるべきですか?という質問がよくなされます。
この質問に対して旧課程では回答が楽でした。
「糖とアミノ酸を徹底的にやって、脂質も次にやれば十分だよ!生命のDNAとかは無視して良いよ!」
といっても割と何とかなっていました。選択分野は結局ほとんどでないと言うのが通例でしたので。
しかし、
新課程で恐ろしい事に、生命分野は必修に!!、、、、
そして、各地の有名国立大学でバンバン、DNAが出るようになりました。
ですが、やはり勉強で力を入れるべきなのは、糖とアミノ酸です。
依然こちらの方が圧倒的によく出ます。なので糖とアミノ酸に注意をしておきましょう。
糖
糖の反応は、何と言っても、
『ヘミアセタール』由来の
ヒドロキシ基に着目することです。
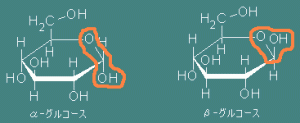
アミノ酸

アミノ酸が結合していくと、タンパク質になります。
この分野の出題傾向としては、あるタンパク質があたえられて、そのタンパク質を分解したとき、どのアミノ酸が使われていたか?
ということが問われたりします。
つまり、『アミノ酸とその性質』を覚えていないとお話になりません。
ここは踏ん張って努力しか
ありません。
また、量計算もありますが、そのとき物質量を毎回計算していては、一生かかっても終わりません。
なので、
ある程度の分子量は覚えてしまいましょう。
脂質
脂質は本当に
問われるところが決まっています。
脂質は高級カルボン酸とグリセリンで、どの脂肪酸が反応したのかを瞬時に判断できれば行けます。
生命
この辺は核酸塩基の範囲が混ざりますので、やはり塩基を覚えておくべきです。

アデニンーチミン(RNA時ウラシル)
グアニンーシトシン
などの核酸塩基の組み合わせは絶対に覚えておかなければなりません。
また、まれですが、構造が与えられてその名前を答えろ!と言う問題も出ますので、その問題のためには、構造式をある程度みてわかるレベルにはしておく必要はあります。
ですが、これは過去問と相談すると言う事でしょう。
いかがでしたか?
かなり天然有機物の範囲は
暗記が多くてしんどいかもしれません。
ですが、覚えた物が、
即点数に直結するのも
この分野のいいところです。
なので、今日紹介した
覚え方、構造の考え方の記事をよく読んで、
出来るだけ頭に定着しやすいように
していきましょう。

 これさえやれば、
あなたは、有機化学に問題なく
取り組めます!
これは電子書籍なので、
あなたのメールアドレスに送ります。
なのでこちらのフォームに
入力してください。
これを入力する事で迷惑メールが来る事は
一切ありません。
学年は、今年の新学年を
選択してください。
これさえやれば、
あなたは、有機化学に問題なく
取り組めます!
これは電子書籍なので、
あなたのメールアドレスに送ります。
なのでこちらのフォームに
入力してください。
これを入力する事で迷惑メールが来る事は
一切ありません。
学年は、今年の新学年を
選択してください。














今、高分子やってます。「ヘミアセタールの構造とは?」などのページがまだないそうなのでお願いします。どのようなページになるのか楽しみにしてます
すみません。なるべく早く出します!