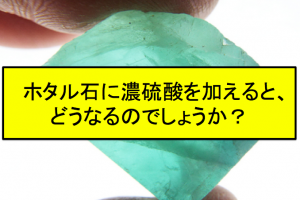こんにちは。



フッ素(F)、塩素(Cl)、臭素(Br)、ヨウ素(I)、アスタチン(At)、テネシン(Ts)からなる第17族元素の総称がハロゲン。
アスタチンとテネシンはわずかな時間しか存在できないため、基本的にはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素の4元素が高校化学では取り上げられます。
フッ化カルシウムや塩化ナトリウムなど、多くの重要な化合物を持つハロゲンですが、単体の性質も重要ポイント。
この記事ではハロゲン単体の性質について詳しく解説しています。
ハロゲン化合物やハロゲンの半反応式の作り方についても、たくさんの記事をアップしていますのでぜひ読んでみてください。
目次
ハロゲン単体の共通点は?
ハロゲンはなぜ反応性が高いのでしょうか?
共通する性質をまとめていきましょう!
最外殻に7つの価電子を持つ

ハロゲン原子が最外殻にもつ電子の数は7つ。
8つの電子を持ちオクテット則を満たすと希ガスと同じ電子配列になり安定するので、ハロゲン原子は強く電子を求めます。
これがハロゲンの反応性が高い理由です!
単体は共通結合して二原子分子になる

ハロゲン単体は、2つの原子が1つずつ電子を出し合い共有結合した「二原子分子」になります。
水素や酸素など、他の非金属の多くも二原子分子を作りますね。
電子1つを得て、1価の陰イオンになりやすい

最外殻に7つの電子を持つハロゲンは、もうひとつ電子を獲得して1価の陰イオンになりやすい性質があります。
したがってアルカリ金属やアルカリ土類金属とイオン結合し、塩を作るのです。
可視光を吸収するため有色

ハロゲンは可視光を吸収するため色づいて見えます。
ハロゲン単体の違いは?
似た性質を持つハロゲン単体ですが、分子量や原子半径の違いから生み出される様々な違いもあります。
分かりやすく、表にまとめてみました!

原子番号が大きくなるほど、融点や沸点が高くなる
分子量が大きくなるほど分子間力が強く働くので、融点や沸点が高くなります。
そのためフッ素と塩素は常温常圧で気体ですが、臭素は液体、ヨウ素は固体です。
原子番号が大きくなるほど、色が濃くなる
原子番号が大きくなるほど、吸収する波長域が広がるので色が濃くなっていきます。
原子番号が大きくなるほど、反応性(酸化力)が弱くなる
ハロゲン単体の酸化力=反応性はフッ素が最強で、原子番号が大きくなるほど弱くなっていきます。
これは原子半径が小さいと原子核の正電荷が最外殻電子に強く働き、電子を取り込む力も強くなるからです。
ハロゲン単体それぞれの性質と用途
ハロゲン単体、それぞれには具体的にどのような性質があるのでしょう?
またどのような目的で使われているのでしょうか?
フッ素

フッ素は全元素中で最大の電気陰性度4.0を持ちます。
したがって反応性が高くほぼ全ての元素と反応するため、単体よりもフッ化水素などの化合物として用いられることが多いです。
しかし半導体や液晶の洗浄などには、フッ素単体がクリーニングガスとして用いられるそう。
汚れを超強力に分解してくれるのです。
フッ化水素の性質について詳しく知りたい人は、この記事も読んでみてください。
塩素

塩素ガスは強い漂白作用や殺菌作用を持ちます。
そのため水の消毒や漂白剤として有用なのですが、有毒なガスの状態では取り扱いが困難ですよね?
そこで、広く用いられているのは塩素を水酸化ナトリウムと反応させた「次亜塩素酸ナトリウム」です。
有毒性を逆手に取り、塩素ガスは第一次世界大戦で人類初の化学兵器「毒ガス」としても用いられました。
次亜塩素酸について詳しく知りたい人には、こちらの記事をどうぞ!
臭素

臭素は非金属元素単体のうち、常温常圧下で唯一の液体です。
しかし容易に蒸発し、赤色の気体となります。
有毒で名前の通り強い臭気があるため、単体が用いられることはほとんどありません。
銀との化合物である臭化銀は写真の感光紙に用いられるので、大判の写真のことをブロマイド(英語で臭素はブロミン)と言うそうです。
ヨウ素

ヨウ素は非常に有用な物質で、日常生活や化学実験でも広く用いられています。
誰でも覚えがあるのは、ジャガイモやご飯にヨウ素液を垂らしてデンプンの存在を確かめる「ヨウ素デンプン反応」の実験。
またヨウ素単体のアルコール溶液は「ヨードチンキ」と呼ばれ、ケガをした時の消毒薬として用いられています。
ヨウ素は人間の必須元素のひとつでもあり、不足すると甲状腺の機能低下が起きることも。
海藻などに多く含まれているので、積極的に食べましょう。
まとめ
ハロゲン単体の特徴、分かっていただけましたか?
- フッ素、塩素、臭素、ヨウ素を「ハロゲン」という。
- ハロゲンは「塩をつくるもの」という意味。
- 最外殻電子は7つのため、もう1つの電子を得て最外殻を満たそうとする。
- 反応性が高い。
- 1価の陰イオンになりやすい。
- 原子番号が小さいほど反応性が高い。
- 原子番号が大きいほど融点・沸点が高い。
- 原子番号が大きいほど色が濃い。